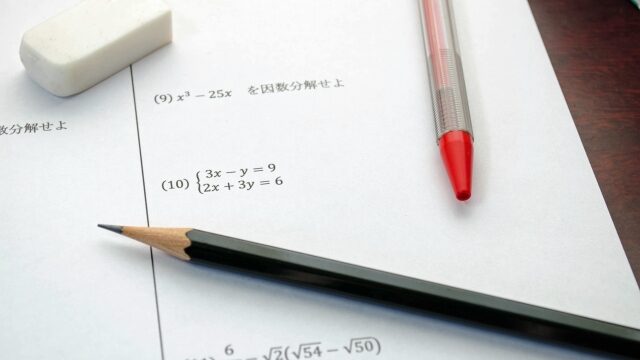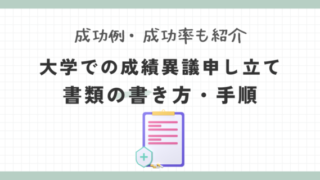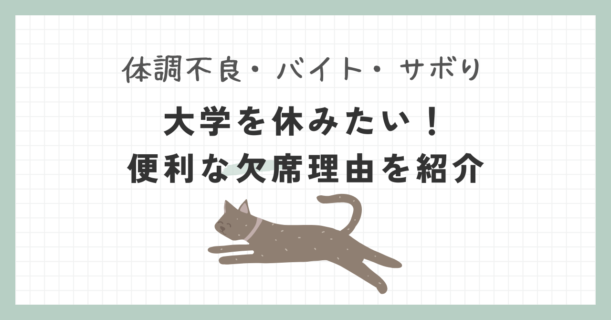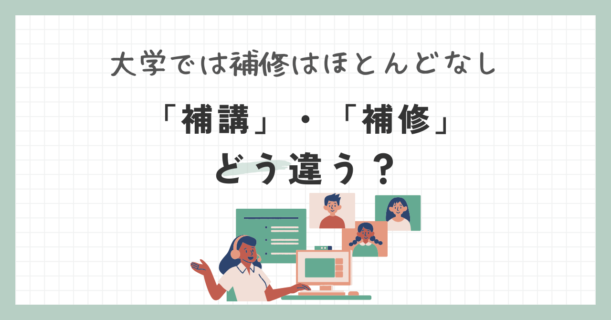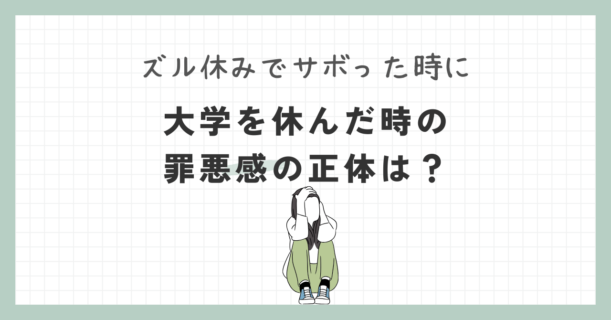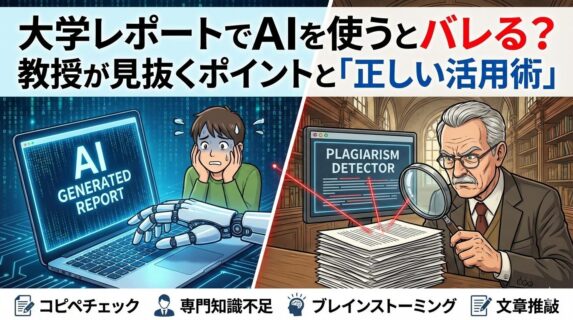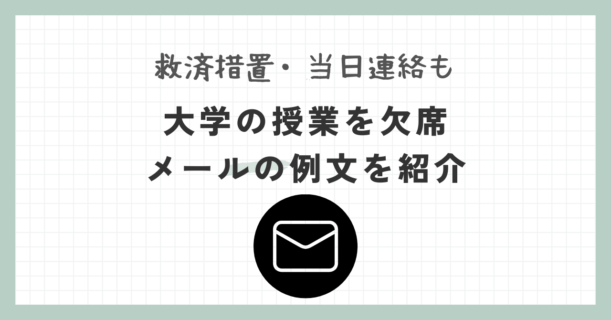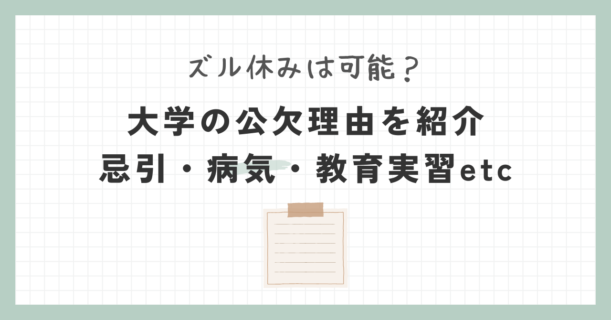追試と再試の違いを解説!大学の単位修得のラストチャンス!

- 「テストの結果が思わしくなかった…」
- 「体調不良でテストを受けられなかった…」
こんな人のために残されているのが、「追試」や「再試」といった救済措置です。
「追試と再試って何が違うの?」と疑問に思っている人も多いでしょう。
- 追試(追試験):病気等で試験を受けられなかった場合の救済措置
- 再試(再試験):試験を受けて不合格だった学生への救済措置
追試と再試の違いについて解説していきます。
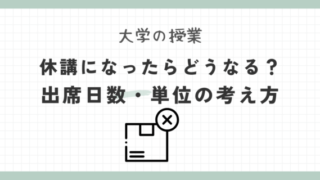
追試(追試験)とは?
追試とは、病気や事故、忌引きなど、やむを得ない理由で考査(テスト)を受けられなかった学生を対象とした救済措置です。
追試の対象となる理由は大学によって異なりますが、一般的には以下のケースが挙げられます。
- 病気
- 怪我
- 忌引き
- 交通機関の遅延
- 感染症による出席停止
- その他、大学が認める理由
「追試」はやむを得ない事情による欠席を救済する措置なので、大学として正式に設定しているケースが多いです。
追試では、考査と同じレベルの問題が出題されることが一般的です。評価方法も定期試験と同様で、合格すれば通常の単位が与えられます。
通常の考査よりは後の日程で行われるため、同級生から問題を聞くことで有利にならないように配慮されるのが一般的です。
再試(再試験)とは?
再試とは、定期試験の結果が不合格だった学生を対象とした救済措置です。
再試を設定しているかは大学によって異なり、筆者の勤務している大学にも公式な再試制度はありません。
いくつかの大学の再試の状況を調べてみました。
- 早稲田大学 社会科学部 → 1科目につき1,000円で受講可能
- 立教大学 → 追試験はあり、再試験はなし
- 東洋大学 経営学部 → 1科目につき5,000円で受講可能
- 埼玉大学 → 再試験は行わない
- 筑波大学 → 再試験制度あり
再試験は、卒業できない学生などへの救済措置であり、大学の方針では制度自体がないこともあります。国立大学に比べると、私立大学で試験料を徴収しての制度を設けていることが多いようです。
再試の難易度は大学によって異なりますが、一般的には定期試験よりも易しい問題が出題されることが多いようです。
評価方法は大学によって異なり、合格した場合でも評価が「可」や「C」などに制限される場合があります。
追試と再試の違い
追試と再試の主な違いは、以下の通りです。
| 追試験 | 再試験 | |
| 対象者 | やむを得ない理由で定期試験を受けられなかった学生 | 考査の結果が不合格だった学生 |
| 実施時期 | 考査終了後 | 考査終了後、 |
| 難易度 | 考査と同程度 | 考査より易しい場合が多い |
| 評価方法 | 考査と同様 | 合格した場合でも評価が制限される場合がある |
| 受験料 | 無料の場合が多い | 有料の場合が多い |
| 制度の有無 | どの大学にもあり | ない大学もある |
追試・再試を受ける際の注意点
追試や再試を受ける際には、以下の点に注意しましょう。
- 追試・再試の申請期限・必要書類:追試を希望する場合は、大学が定める期限内に申請し、必要な書類を提出する必要があります。期限や必要書類は大学によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
- 追試・再試の受験資格・実施時期:追試・再試は、全ての学生が受けられるとは限りません。受験資格や実施時期は大学によって異なるため、大学の規程を確認しておきましょう。
- 追試・再試の難易度・評価方法:追試・再試の難易度や評価方法は、大学や科目によって異なります。事前に情報を集め、十分な対策をして臨みましょう。
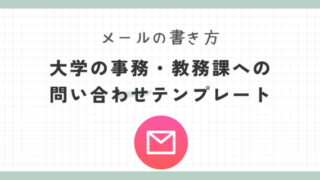
追試・再試以外にもある救済措置
大学によっては、追試・再試以外にも以下のような救済措置が設けられている場合があります。
- レポート提出:試験の代わりに、レポート提出で単位を認める
- 追加課題:試験の代わりに、追加課題の提出で単位を認める
- 特別試験:病気や怪我などで長期欠席した場合の特別対応
これらの救済措置についても、大学によって条件や内容が異なるため、授業の担当教員にも確認するといいでしょう。。
まとめ:国立では再試験は少ない
追試と再試の違いについて解説しました。
- 追試(追試験):病気等で試験を受けられなかった場合の救済措置
- 再試(再試験):試験を受けて不合格だった学生への救済措置
追試・再試は、単位修得のラストチャンスです。万が一の時に備えて、追試・再試の仕組みや注意点を理解し、大学の制度を確認しておきましょう。
しかし、最も大切なことは、日頃からしっかりと学習し、日常点・レポート・テストで良い結果を出すことです。計画的に学習を進めるといいでしょう。