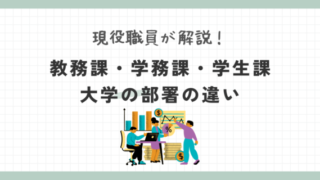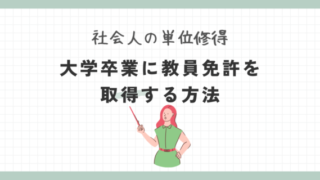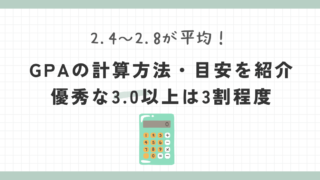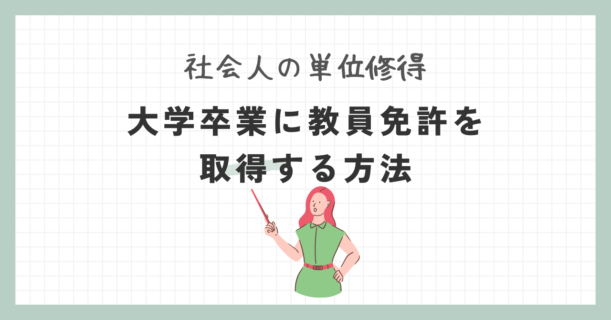教育実習・介護等体験はいらない?代替措置の現状(令和7年2月現在)
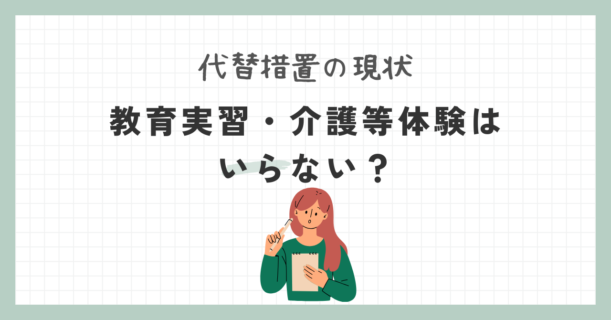
令和2年の新型コロナウイルスの流行以来、教員免許取得に必要な教育実習・介護等体験は代替措置での対応が可能になっていましたが、令和7年以降ほぼ元通りになりました。
- 令和7年度から、教育実習・介護等体験ともに、ほぼコロナ前に戻った
- 過去に行っていた代替措置を紹介
- 「介護等体験はいらない」という意見もあるが、なくならない可能性が高い
令和7年度の教育実習・介護等体験の実態をお伝えします。
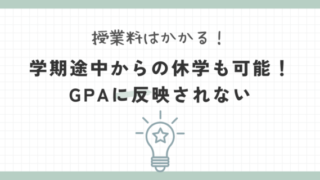
教育実習と介護等体験の内容
教育実習
まず、教育実習の基本的な事項ですが、「中学校の第一種免許を取得するためには3週間、高校の第一種免許を取得するためには2週間の教育実習に行く」必要があります。
中学・高校両方の免許を取得するためには教育実習を中学・高校どちらで行ってもいいというルール(その場合は3週間以上)や、より長い期間の教育実習を求めている大学もあります。
介護等体験
介護等体験は5日間社会福祉施設で、2日間特別支援学校で行うことを文部科学省が求めています。
- 「社会福祉施設」(5日間の実習)は、障害者施設や老人ホーム等です。介護が必要な方が過ごす施設で、障害や病気との向き合い方を学びます。
- 「特別支援学校」(2日間の実習)は、心身に障がいのある学生を教育する施設です。実際に教員になった際にも障がいを持った子を受け待つ可能性はあり、専門に受け入れている特別支援学校での体験を求めています。
感染症の影響が大きいため、レポートなどの代替措置を認めていましたが、令和7年度からは特例措置を終了し、原則現地での体験を行うことが示されました。
※社会福祉施設の受け入れが慎重な場合、特別支援学校で7日間の実習を行うことも認めています。
文部科学省:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う介護等体験の実施における特例措置の終了について(周知)
教育実習の代替措置
令和2年度の代替措置
令和2年度は、教育実習の受け入れを中止する中学・高校が多く、大学は対応に追われました。
大学に教員養成の課程(教育学部等)がある場合は、教育学部で対応方針を決め、他の学部で教員免許を取得する学生も同様の対応としています。
一般的には、教育学部では90%以上の学生が教員免許を取得しており、文学部や理学部などの学生で5〜10%の学生が教員免許を取得するというイメージです。
教員養成課程がある大学では附属の中学・高校を設置している大学があります。姉妹組織となるため、大学から附属学校へ協力依頼が出され、母校で対応できなかった学生への代替措置(救済措置)を行っていました。
「埼玉大学」の教育実習生を「埼玉大学教育学部附属中学校」で受け入れるようなケースです。
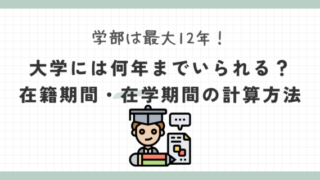
令和3年度の代替措置
(1)教育実習の実施に関する特例
新型コロナウイルス感染症の影響により、大学等が令和2年度から令和4年
度までの間に教育実習の科目の授業を実施できないことにより、教職課程を置
く各国公私立大学、各指定教員養成機関(以下「大学等」という。)に在学す
る学生又は科目等履修生が教育実習の科目の単位を修得できないときは、課程
認定を受けた教育実習以外の科目の単位をもってあてることができることと
すること。
中略
教育実習特例は真にやむを得ない場合にのみ活用することとし、また、教育実習特例を活用する場合やイ、ウによる場合においても、新型コロナウイルス感染症の状況に十分注意しつつ、学生が学校教育の実際を体験的、総合的に理解できる機会(例えば学習指導員としての活動等)の活用を積極的に促進することが期待されること。
要点をまとめると、教育実習は教員免許取得に非常に重要な機会のため、原則「従来どおりに行う」としています。
一方で、コロナにより、教育実習校が休校になった場合や学生がコロナ・濃厚接触者になった場合に備えて、代替措置を用意することを文科省は求めています。
実際に、令和3年度には下記のような対応となったことがありました。
- 実習先の中学校でコロナ感染者が出てしまい、教育実習は9日間のみになったため、残りをレポートで対応。
- 実習学生が発熱してしまったため、別日に大学の附属中学校で1週間の代替実習が行われた。
代替措置を利用した学生もいましたが、90%以上の学生が従来どおりの期間、教育実習を終えています。
介護等体験の代替措置(レポート)
令和2~6年度の代替措置
介護等体験に関しては、障がいのある方が生活する施設に行くことが前提になっているため、感染症の影響がより深刻に考えられています。
文部科学省は、教育実習と比べて、簡単に代替措置の適用ができるようにしました。
介護等体験を免除する者として、令和2年度から令和5年度までの間において介護等体験を行うことを予定していたにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により介護等体験を行う施設における受入れが困難な状況にあることその他これに類する事由により介護等体験を行うことが困難な者であって、次のアからキまでのいずれかに該当するものとしたこと。
中略
エ 在学する大学等において、令和5年度までに、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が開設する免許法認定通信教育の科目に係る印刷教材の学修の成果を確認する措置を受けた者
様々な代替措置が想定されていますが、印刷教材による学修の成果を確認で代替措置とした大学が多いです。全ての代替措置は上記、文部科学省の通知を参考にしてください。
【具体的な代替措置内容】
定められた視覚障害・聴覚障害いずれかのテキストを購読し、1500字程度のレポートで報告することで、介護等体験の代替措置とできることにしています。
(厳密には、やむを得ず代替措置を行うという申請を学生がして、レポート内容を大学で承認する流れですが、ほぼ100%の学生が代替措置で対応しています。)
7日間、学外での実習を行っていたことを考えると、学生の負担は少なくなったと言えます。
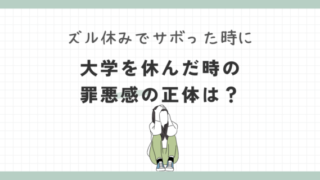
教育実習・介護等体験はいらない?
教育実習・介護等体験の代替措置が可能となったことで、多くの学生が考えているのは、そもそも「教育実習・介護等体験」はいらないのでは?ということです。
教員になった際の職場である学校での実習は必要でも、「介護等体験はいらない」と考えている学生が多いのが実情です。
実際に文部科学省の通知では、「希望者は介護等体験をしても良い」となっていますが、大学内で1人も希望する学生がいなかったこともありました。
そもそも介護等体験の目的は、「個人の尊厳」と「社会連帯の理念」に関する認識を深めることです。
教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ教員の資質向上及び学校教育の一層の充実を図るため、小学校及び中学校の教諭の普通免許状取得希望者に介護等体験が義務付けられています。
「障がい者・ダイバーシティ人材への配慮」「教員から学生への暴力事件」等が多く報じられるなど、現場経験と多様性への理解の重要性は増すばかりです。
実際にコロナ禍があけ、教育実習・介護等体験は復活しました。
教員を志望する学生は、介護等体験を受けていなくても(代替措置で対応できた学生も)、適切な考え方を採用面接などで示せる必要があります。以下の視点を持つと、理解が深まるでしょう。
- 障がいを持った学生の指導にどう活かすか
- 障がいを持った方と交流した経験から、どのようなことを考えたか
- 性的志向に悩みを持った学生から相談されたらどのように対応するか

まとめ:介護等体験の代替措置は終了
令和7年度以降、教育実習・介護等体験ともに代替措置での対応がほぼ終了ました。
現場での教育実習・介護等体験が減ったことをラッキーだと考えていた学生は多いと思います。
一方で、障がい者教育などは、これまでに増して重要になってくるでしょう。現場を体験していない学生が教員になることが教育現場の質低下につながらなければと教育者は懸念しています。
介護の実体験を行わなかった学生も、教材などを読んで、多様性(ダイバーシティ)に対しての理解を深めておくことは欠かせません。
本サイトでは、大学のルールに関してわかりやすく発信していますので、他の記事も読んでもらえると嬉しいです。