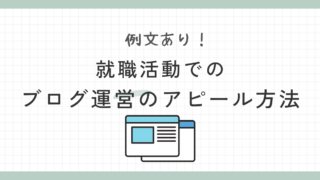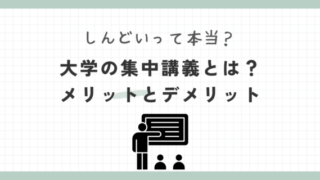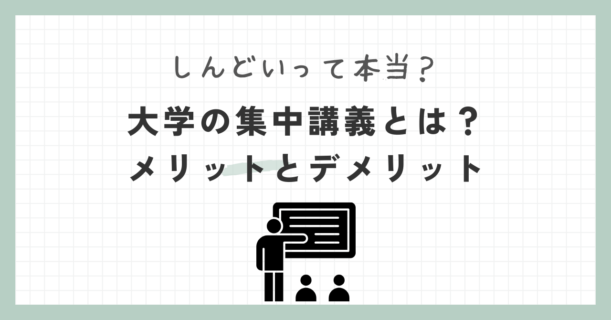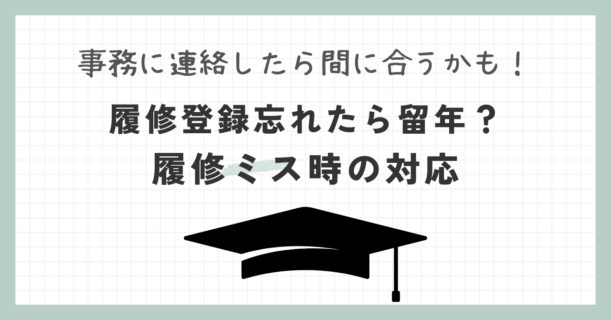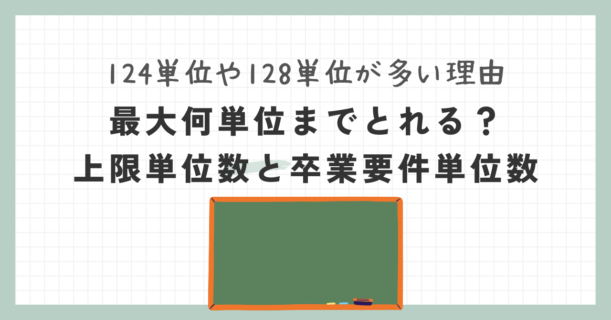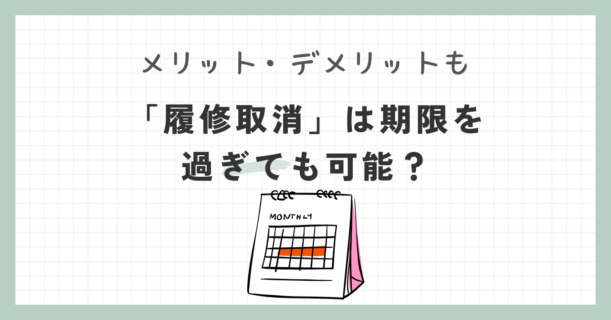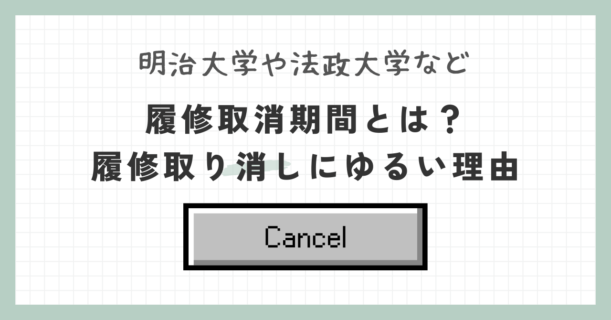大学で全休の日を作ったらなにする?メリット・デメリットも紹介
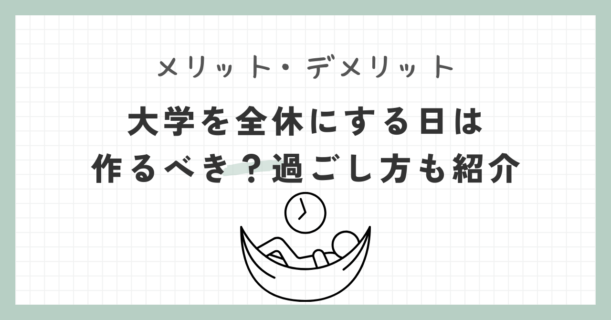
- 大学の時間割どうしよう
- 全休は何曜日がいい?
- 1年生でも全休の日を作れる?
こんな悩みがある方に記事を書きました。
大学の時間割で授業をいれない曜日を「全休(ぜんきゅう)」といいます。
- 全休を作るべきかは人による!全休を作るべき人、できることを解説
- 全休のメリット・デメリットを紹介
- 全休日が選べるなら月・水・金のいずれかがおすすめ
大学4年間全ての学年で、全休の曜日を作っていたことがある現役大学職員の筆者が解説していきます。
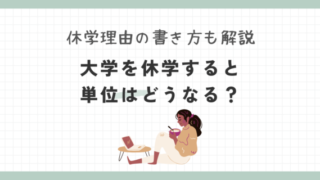
全休を作るべき人
まず、全休を作るべきかは人によって異なります。以下の2点に当てはまる人は全休を作るべきだと考えています。
- 大学までの通学時間が長い人
- 全休日にやることがある人
どちらにも当てはまらない場合はメリット・デメリットから考えるといいでしょう。
大学までの通学時間が長い人
大学までの通学時間が長い人は、全休日を作るのがおすすめです。1日分の通学時間がなくなることで時間を効率的に使えます。
筆者も、大学時代は1時間30分ほど通学時間がありました。往復で3時間使うのはもったいないと考えて、全休を作って、家での予習復習やバイトに当てていました。
全休日にやりたいことがある人
やりたいことがある人は全休の日を作って、大学に行かない日を週に3回作るのもいいでしょう。
筆者の友人は、ディズニーランドでアルバイトをしていました。
当時、最低でも週3日はシフトを入れる必要があり、大学と離れているディズニーランドバイトのため、全休を作っていました。
バイトに限らず、地元の活動・趣味の時間のために全休を作るのもいいでしょう。
関連記事:対象作品も紹介!無料で試せるおすすめのサブスクリプションサービス3選
全休のメリット
全休のメリットは主に以下の3つです。
- 自由時間が増える
- バイトの融通が効きやすい
- 混まない平日に出かけられる
自由時間が増える
大学に通わない日が土日を含めて3日になるため、自由時間が増えます。
毎日授業を入れていると常に5日連続で大学に通う必要がありますが、全休を作るとゆとりが生まれます。
自由時間であると同時に、余裕を持って授業の予習復習ができるのは大きなメリットです。
バイトの融通が効きやすい
全休日があると、バイトの融通が効きやすく、バイトの選択肢が増えます。
平日の夜と土日よりも、土日を含めた3日間で日中にシフトに入れるほうがバイトの需要は多いです。融通が効くので、いろんなバイトに挑戦できます。
関連記事:大学生必見!本当に向いてるバイト・仕事の見つけ方【3つの方法】
混まない平日に出かけられる
全休の日があると、平日に出かけられます。
買い物・レジャー・映画など、平日の昼間は空いていて、場所によっては安価に楽しむことができます。
平日に時間をとって楽しみたい趣味がある人は全休を作るといいでしょう。
全休のデメリット
全休にはデメリットもあり、以下の3つが挙げられます。
- 好きな授業を受けられない
- 授業がある日は忙しい
- 全休日のイベントに参加しづらい
好きな授業を受けられない
全休を作ると決めた場合、必修科目が無い日を全休にするのが基本です。全休にすることで、履修できない授業が出てきてしまいます。
せっかく大学に通っているのに、好きな授業を受けられないのはもったいないです。
翌年も同じ先生で同じ授業が開講されるとは限りません。
授業がある日は忙しい
全休を作った場合、残りの曜日に授業時間が偏ります。
1.2年生の場合は、1日4コマ以上入る曜日も多くなるでしょう。4コマ以上あると予習復習・レポート作成・テスト勉強がきつくなります(授業の中身にもよりますが)。
テスト期間には全休日に入れていたバイトを休むなど、調整が必要です。
全休日のイベントに参加しづらい
全休日を作っているとサークルなどのイベントに参加しづらいのもデメリットの1つです。
自分が休みの日に練習や飲み会がスケジュールされてしまうこともあります。
多くの友達と楽しいキャンパスライフを送りたい人は、全休日を作らないほうがいいかもしれません。
関連記事:フル単の達成割合は約半数で当たり前!GPAと文系理系の違い
全休に関するQ&A
必修科目があって全休にできない
学部によっては必修科目が全曜日に設定されており、全休を作れないこともあります。
必修科目を翌年度に取るということも考えられますが、留年の可能性が高まるため、あまりおすすめはしません。
理系学部や理系のゼミに所属すると、全休ができないという人も多いです。
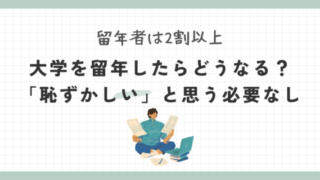
全休は何曜日がオススメ?
好きな曜日を全休にできるのなら、水曜日がいいでしょう。5日間の授業日を2日ずつに分割でき、予習・復習の調整を組みやすいからです。
旅行や帰省の予定を入れたい場合、月曜・金曜にして3連休を作るのもいいですね。
ただ、1日全休にするだけでゆとりは生まれるので、曜日にこだわらず好きな授業を履修して、空いた日を全休にするのがおすすめです。
全休日の過ごし方は?
全休日は、バイト・趣味・副業など、学業以外に時間を使いながら、テスト期間などは学業にも時間を割くといいと思います。
筆者が全休にしていた時は、夕方からはバイトを入れて、日中は映画鑑賞やレポート作成に当てていました。
全休を2日作ることは可能?
全休2日は、文系の2年生以上だと可能な人が多くなります。理系や1年生は現実的ではありません。
通学時間が長い人であれば、全休日は地元でバイトを入れるなど効率的に時間を使うといいでしょう。大学の近くに住んでいる人で、特に全休日のスケジュールが決まってない人にはあまりメリットはないでしょう。
週3日の通学だと、「定期を買わないほうが安い?問題」も出てきます。
履修登録が済んでいても履修取消期間がある場合は、後から全休を作ることも可能です。
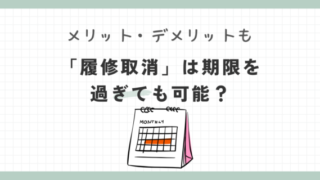
まとめ:大学が遠い人は全休日を作ろう
大学生の全休について紹介してきました。
- 通学時間が長い人は全休を作ると効率的に時間を使える
- 全休を作ることで、他の日が忙しくなるなどデメリットも
- 特にやることが決まっていなければ、全休なしでもOK
筆者は通学時間が長かったため、全休を作って効率的な時間の使い方を重視していました。
しかし、大学生には長い休暇期間があるので、授業期間は大学生活を楽しんで休暇期間にバイトや趣味を楽しむというのもいいでしょう。
バイトに限らず、ブログアフィリエイトや動画編集での収入獲得に挑戦するのもオススメです。