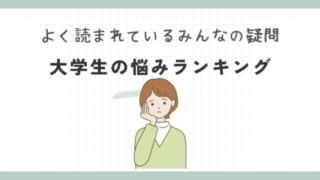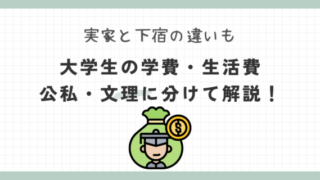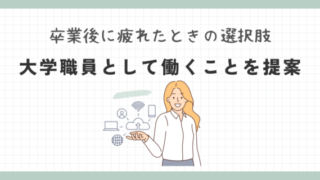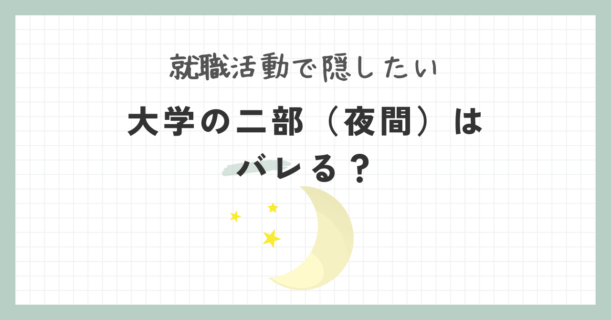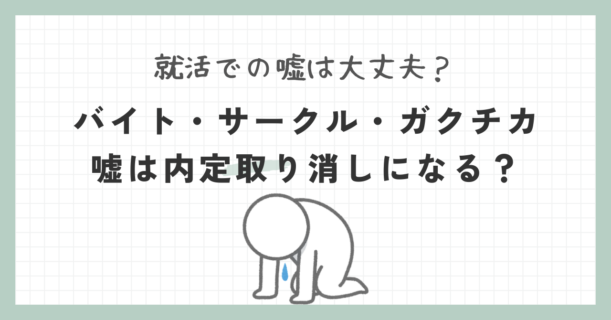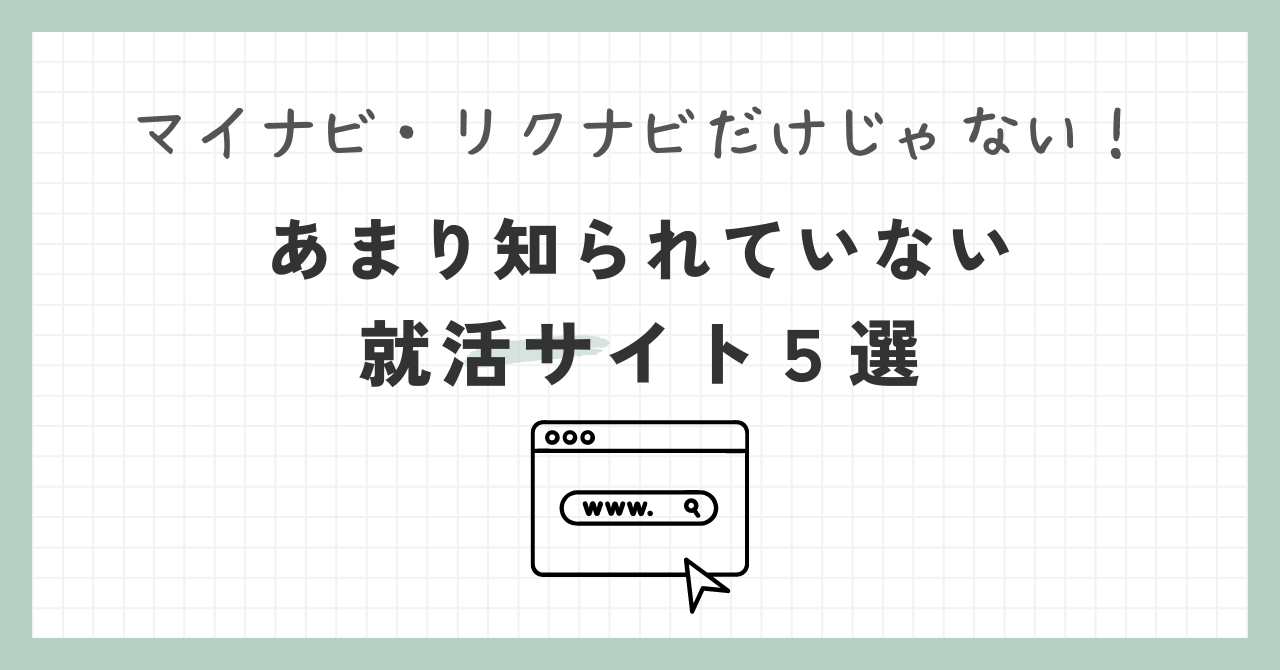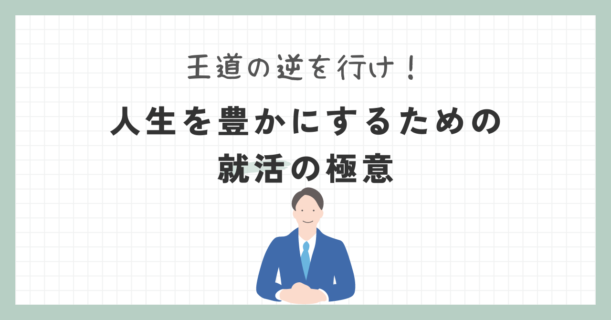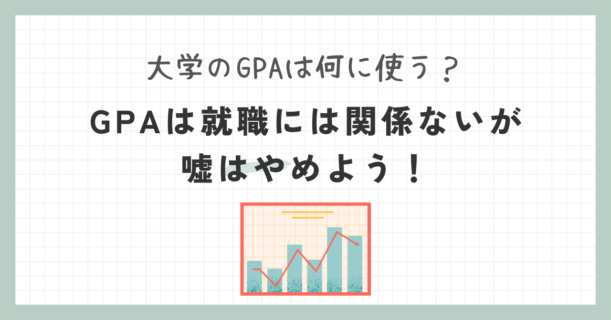大学は就職予備校じゃない?就職予備校と言われる理由を考えてみた
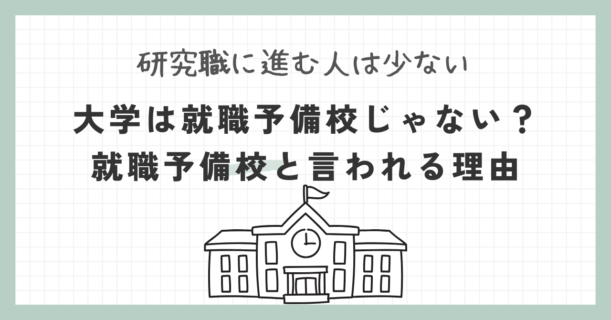
「大学は就職予備校のようなもの」と揶揄されることがあります。
確かに大学卒業後、多くの学生が就職しますし、偏差値の高い大学ほど人気企業に就職していく傾向にあります。
「文部科学省の視点」「学生の視点」も含めて、大学の就職予備校化について考えてみます。
関連記事:就活は王道の逆を行け!人生を豊かにするための就職活動の極意
「大学は就職予備校」という揶揄
大学は就職予備校と言われるのには、以下の意味があると考えています。
- 大学は本来、教育・研究組織なのに就職に重点が置かれている
- 大学院への進学率が低く、ほとんどの学生が就職する
- 教育・研究力の高さよりも、就職率の高さが学生に評価される
本来であれば勉強・研究したい専門分野があって大学に進学すべきなのに、「就職をするために大学進学する人が増えている」という状況を表しています。
実際に大学の学士課程修了者(学部卒業者)のうち、進学者は10-12%ほどです(参考:文部科学省 進学率の推移)。学部を卒業した8割以上が就職しています。
就職を意識しないで大学進学する以下のようなケースは少ないと思います。
- 当初から研究職を目指して、大学進学
- 興味のある分野の研究が盛んという理由で、低偏差値の大学へ進学
- 定年後に興味のある学問を深めるため、大学へ進学
「教育・研究」より「就職」を意識した大学選びには問題があるのでしょうか。
文部科学省から見た大学
文部科学省のホームページには、大学について以下のように記述されています。
大学等の高等教育機関は、多様な教育研究を展開し、社会で活躍する人材の輩出や、社会に変革をもたらす研究成果の創出など、知の基盤としての役割を果たします(参考:文部科学省 大学・大学院・専門教育)。
また、日本の学校教育制度を定める「学校教育法」では以下のように定められています。
第五十二条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
これらの記述から、大学での役割は次のように整理できます。
- 学術の中心として、知の基盤となる機関
- 広く知識を授けること、研究を深めることで社会貢献を行う
- 具体的には、社会に人材輩出・研究成果の創出などを行う
研究成果の創出は学部4年間だけでは難しいという理解になるでしょう。
一方で、社会への人材輩出という目的がある以上、「大学が就職予備校」となっていても問題ないように思います。
学生から見た大学
多くの人が大学に通う理由は何でしょうか。
周りの大人に大学を進められる
親に言われて大学に通う人も少なくありません。よく言われる理由としては以下のようなものがあります。
- 高卒と大卒では生涯年収が違う
- 大卒でないと就職できない企業が多い
- 高卒では結婚相手が絞られる
確かに「大卒のほうが生涯年収が高い」「大卒以上を条件にしている求人は多い」「結婚相手の条件を大卒以上にしている人は多い」というデータがあります。
人生におけるコスパを考えると、大学に通ったほうがいいという意見にも頷けます。
就職実績が良い偏差値の高い大学に行きたい
大学であればどこでもいいわけではなく、大学間でも年収に差があり、さらに年収ごとに婚姻率の差があります。一般的に偏差値の高い大学ほど、平均年収が高くなります。
そのため、学生はできる限り偏差値の高い大学を目指すことになります。
大学は「就職先へのチケット」の役割もあります。大学のランクによってチケットの効力は異なり、同じ大卒でも偏差値によって分類されています(一般的に学歴フィルターなどと呼ばれます)。
企業では「学歴フィルターはない」と言いますが、内定者の出身大学をみると有名大学ばかりということはよくあります。
この事実をもとに、就職先の選択肢が増えるように「偏差値の高い大学」を目指すのです。この現象(就職先の選択肢が多い大学が学生に選ばれる状況)が「大学の就職予備校化」と言われているのだと考えています。
また、専門資格取得のために大学に通う人もいますが(例えば医師・教師など)、就職のための資格取得という面が大きいため、就職のために大学に行く学生と大差はないと考えられます。
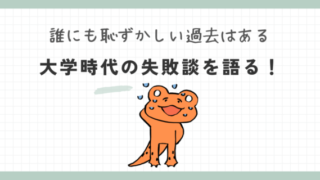
まとめ:就職予備校かもしれないが問題ないのでは?
大学が就職予備校と呼ばれている理由、大学の役割について紹介してきました。
大学が「社会への人材輩出」を目的の一つにしている以上、就職を重視するのは当然のことです。一方で、「研究成果の創出」のためには多くの学生を大学院に進学させ、研究者を要請すべきという意見もわかります。
修士号や博士号取得者が就職しやすい世の中であれば、「就職予備校化」を抜け出せるかもしれません。
企業が学生の採用基準を大幅に変える(学歴・コミュニケーション能力ばかりではなく、在学時に得た知識や成績を重視する)ことがないと、卒業後に就職する大学生が多い以上、就職予備校といわれてしまうのでしょう。