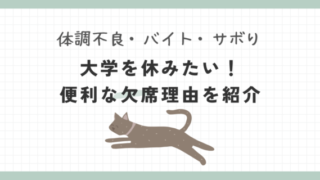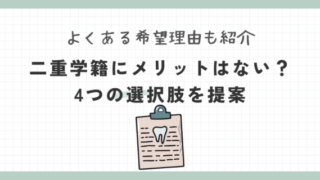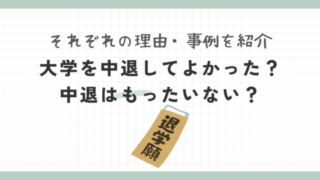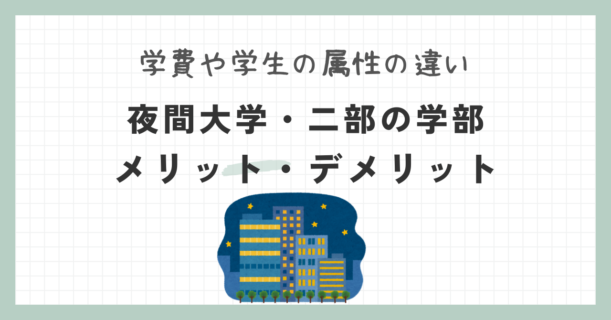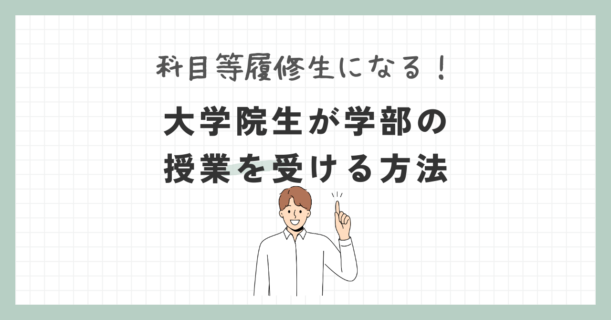大学で単位制度の実質化と修得上限単位数が定められている理由・メリット
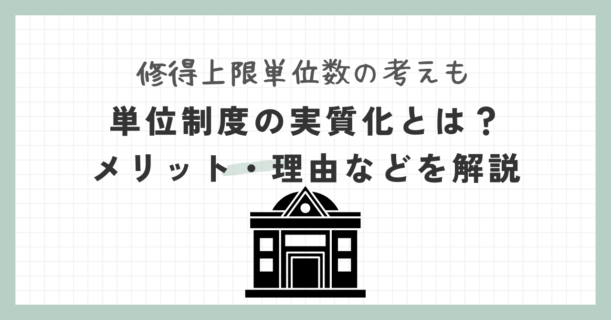
「大学を卒業するには124単位が必要になる」のを知っている人は多いでしょう。
「単位」や「卒業要件」という言葉は、文部科学省が定める「大学設置基準」等に掲載されています。
- 大学の制度の「単位」や「修得上限単位数」について、
大学設置基準をもとに解説 - 「単位制度の実質化」について詳しく解説
本記事では、文部科学省の大学設置基準等を読み解いていきます。
結論としては、単位制度の崩壊を避けるため、修得上限単位数を決めて、学生の学習を管理していることになります。
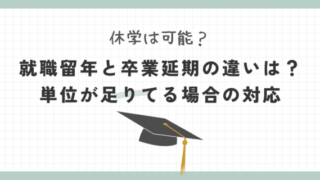
単位制度の実質化とは?
「単位制度の実質化」とは、日本の大学で用いられている45時間の学修を1単位とする考え方のことです。
(単位)
第二十一条 各授業科目の単位数は、大学において定めるものとする。
2 前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
一 講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。
二 実験、実習及び実技については、三十時間から四十五時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、大学が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。
三 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮して大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。
3 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
単位制度の実質化のメリット
単位制度の実質化の考え方に則ると、実際に授業を受けている時間以外の予習・復習の時間を含めて45時間の学習を1単位としています。
- 大学側・・・45時間丸々授業を行う必要がない
(人件費を抑えられる) - 学生側・・・45時間丸々授業を受ける必要がない
(勉強をせずに、遊びやバイトができる)
大学側も学生側も、予習・復習の時間とみなすことで実際の授業時間を少なくできるというメリットがあります(全員にメリットとは限りませんが)。
単位制度の実質化への疑問
日本では「単位制度の実質化」が疑問視されています。
文部科学省の定める大学設置基準では、1単位の修得に45時間相当の学習が必要とされています。
大学1年間で、40単位ほどの単位を修得する学生は少なくありません。長期休暇を除いた半期を考えると、4~7月の約4ヶ月で20単位を修得する計算になります。
20単位×45時間=900時間の学習時間が必要になります。
900時間を4ヶ月120日で割ると、1日あたりの学習時間が7.5時間になります。
アルバイトやサークルに力を入れている大学生が、休日を含めた1日平均7.5時間の学習を行っているのかは疑問が残ります。
「単位制度が実質化」されているのであれば、1単位を与えるのに、45時間学習を行っているという考えになりますが、実態はそうなっていないことに多くの人が気づいています。
大学生に適切な学習時間を取らせて単位を与えることで、単位制度を適切に運営しようという考えが「単位制度の実質化」です。
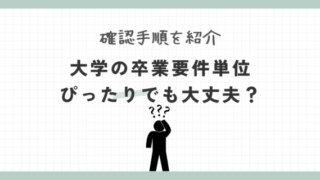
学期ごとの修得上限単位数を定めている理由
大学設置基準から、文部科学省の「単位」に関する考え方を読み解くことができます。
ここから、大学が修得上限単位数を定めていることが説明できます。
【前提】
1単位45時間
講義・演習に関しては、15~30時間までの授業を行う。
残りの15~30時間は自習によって行う。
単位制度を定めている以上、大学での授業とともに自習を行うことが前提とされているため、学期ごとに修得できる単位数を学部・学科ごとに定めるべきである。
また、修得できる単位数は3年間で修得できる上限には設定しない。3年間ですべての単位を修得できることは単位制度の実質化の否定にも繋がると考えられています。
一方で、優秀な学生は45時間以下の学修をもって、もしくは普通の学生以上の学習時間を確保しているという考え方から、上限単位数以上の単位数修得の設定を否定していません。
優秀な学生は3年間で早期卒業することができる大学・学部もあります。
学期ごとに学習できる時間が決まるため、「修得上限単位数」を定め、単位制度を実質化することをアピールすることになります。

3年次後期に履修できる単位数が極端に少ない大学
上限単位数を大学が定める理由について説明してきました。
学年ごとの上限単位数を定めており、大学によっては3年次後期の修得可能上限単位数を極端に少なくしている大学があります。理由は主に2点あります。
- 1・2年次には集中して多くの科目の修得を推奨し、3年次の修得可能単位数が相対的に少なくなるというもの。
- 就職活動や卒業論文等を考慮し、3年次後期の修得可能単位数を少なくしているというもの。
124単位を単純に4で割ると、1年31単位ですが、低学年時には学修の習慣をつけるため、また基礎的な内容が多いため、多くの授業を修得できるようにし、3・4年時には進学・就職準備として少なめの単位を設定しているということになります。
本来であれば、好きな学年に好きな単位数を取れることが学生にとっては好ましいですが、文部科学省の示す「単位制度の実質化」のため、学年・学期ごとの修得上限単位数を定めているということになります。
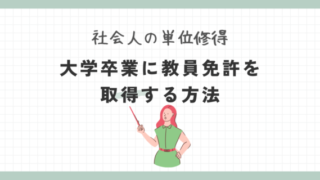
まとめ:単位制度の実質化は日本の課題
大学は「単位制度の実質化」のため、学年・学期ごとに修得できる単位上限数を定めています。
自由に単位を修得できてしまうと、簡単な授業などをたくさん履修して、早い段階で卒業要件を満たしてしまう。
そうすると「単位制度の崩壊」に繋がると考えられ、上限を定めて管理している
他にも、大学に関するルールをわかりやすく解説していますので、併せて読んでいただけると嬉しいです。